小径ドリルとは

小径ドリルは僕の感覚ではφ0.5~φ2㎜の径かなと思います。
よく折れるので折れないような加工方法を紹介します。
折れないようにする為には
小径である程、折れてしまう確率が高くなります。
絶対に折れないとは言い切れませんが、折れないようにする為には、以下の方法を試して下さい。
3Dまでの深さの場合
- なるべく小さいモミツケをする。
- φ1ならφ1のモミツケドリルを使用します。
- 口元1ミリまで超硬ドリルを使用。
- モミツケ後、同じ径の超硬ドリルで1~2ミリ入れる事で、より一層、芯が出ます。
- 超硬ドリルは折れやすいですが、口元でしたら、折れても取れます。
- 面取り
- φ3などの小さなスポットドリルで面取りをします。
- ステップを細かく入れる
- 0.5~1ミリのステップを入れます。
- ハイスドリルを使います。
- ハイスは、超硬より折れにくいです。
- コーティングされているドリルを使用します。
- 送りを落とす
- φ1なら送り0.01くらいにします。φ0.05なら0.005ほどです。
- シャンクはなるべく太い径を使う。
- ドリルチャックで掴みシャンク部分ピックで当てて振れ回して、芯ズレがない事を確認します。
- 芯振れの無い機械、チャックを使用しましょう。
- 常に新品を使います。
- 一度、ドリルチャックから外したら、それでお役目ゴメン。
- 先端の欠けは、分からないので捨ててしまいます。
- 小径ドリルは安いので、中古として残すのはやめます。
- 折れ検知
- マザックはありますが、Mコードに折れ検知(M35)を入れておくと、折れた時、次の加工に移らず止まります。
深穴の場合
深穴の場合は上記の内容にくわえて、さらに条件をつけます。
- 3D深さまでは一般のドリルを使用します。
- 3D以降はロングドリルを使用します。
- ロングドリルは、送りを一般ドリルより遅くします。
- φ1なら送り0.005。
- ロングドリルはなるべくシャンクを深くつかみます。
- ワーク干渉しない限りドリルチャックでシャンクをつかみます。
- トンボ加工
- 表と裏の芯が少しズレてもいいのなら、表面から加工と同時に基準面をすて削りして、裏からすて削りを基準に追って穴を加工します。例えば、φ1ミリの穴を表から加工すると同時にφ20穴も加工して、裏にしてφ20穴を基準にφ1穴を加工します。この場合φ20穴は面粗度はキレイにしておきます。ピックで振れ回して芯出しして原点入力します。
ドリル加工不可能と思える事
- 板厚がドリル径の20倍以上。
- チタン、SUS304などの難削材。
- 半がかりのような形状。(半月形状)@フラットドリルなら3Dまで可能。
上記な場合は、ドリル加工自体が不可能な事があります。
設計変更、口元10㎜を座グリにするとかの変更。
難削材で板厚3ミリまでならレーザーで打ち抜きなど、加工自体を見直す必要があります。
面取り
φ1までなら、なんとか面取りは出来るかもしれませんが、それ以下の径でしたら、面取り出来ないので、少し大きなドリルで面取りを入れるか、油砥石でバリを取るようにします。
小径ドリル販売メーカー
リンク
ナチが種類が豊富です。一般的なドリルからロング、フラットドリル、難削材用、マイクロドリル(φ0.01㎜~)があります。
または日進工具です。
リンク
OSGはφ0.5㎜~のようです。


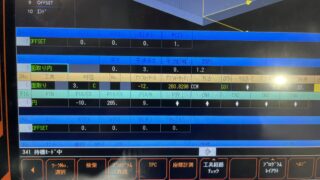

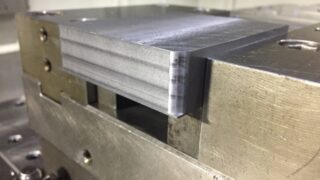
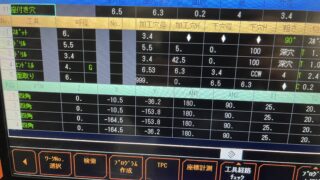










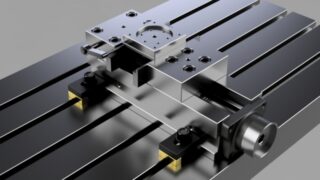



コメント